ごうしゅいも、祖谷いも、下栗いも、

ごうしゅいも、祖谷(いや)いも【写真は、落合いも】
ごうしゅいも、ごうしゅいも、ごういも、ごうしも、源平いもとも呼ばれて
いるものであり、古くから栽培されている皮色が赤や白などいろいろな品種の
総称です。
徳島県西部の三好郡東祖谷山村に万延元年(1860)頃から栽培され、先祖代々
受け継がれ主として自家消費されてきたものです。
祖谷の地は痩せているといわれていますが、標高があり、寒冷を好むジャガ
イモに合ったのかこれまで生き延びてきたものを地域の活性化のため商品化が
できないものかと1900年ころから検討されてきました。長い間栽培されて各
種ウイルス病などに罹っているため、この除去もなされました。
しかし、「男爵薯」に比べると概して小粒で卵形が多く、収量も半分割程度
しかないが、紅や白の組み合わせ販売もされています。
平成9年度(1997)から「地域特産作物発掘導入促進事業」において、東祖谷
山村、西祖谷山村、一宇村で商品化への取り組みを開始し、「源平いも」の名
の商品化もなされ大阪、京都などに販売しています。
標高がある急勾配のやせた畑に適しており、普通の畑に植え付けるとサクサ
クした歯ごたえのないいもになってしまうとか。
味は濃く、栗味に近いものがあり、概して煮くずれしないので、おでん・カ
レー等の煮物に最適で、“でこまわし”と呼ばれる田楽(じゃがいも・石豆腐
・こんにゃくを串に刺し、ゆずみそを付けて火であぶったもの)にも使われて
います
。
日本三大秘境 東祖谷に塊茎写真が載
っています
下栗芋、下り芋、甲斐芋
16世紀の前半にジャガタラ経由でわが国に入ったジャガイモは、高野長英
の著作などによれば、18世紀半ばの明和年間に甲斐国で広まり、その後信
濃、飛騨、上野、武蔵などへ伝わったとされています。
長野県遠山郷南信濃村では、急峻な南アルプスの斜面がきりひらかれて、
「ゼリ畑」(礫の畑の意)と呼ばれているそうです。山地ですが、2億年前の古
生層からなり比較的肥えており、粘板岩や砂岩の地層は山鍬で耕すと耕地化し
やすい。 標高1000mの上村下栗集落では、良質なジャガイモがとれるこ
とから、「下栗芋」と呼ばれています。ここで使われてきた品種名は
定かではありませんが、赤いのは終戦後北海道から導入された「アーリーロー
ズ」との説もあります(下伊那改良普及センター阿南支所中村武郎)。
通常、ジャガイモは連作すると忌地現象を起こすが、遠山郷の二度芋栽培で
はそれがみられないのは、古生層の岩石が風化して、常に新しい耕土が供給さ
れているからと言われています(長野県立歴史館館長 市川健夫)。
飯田下伊那地方では、遠山産のものを限定して二度芋と呼びます
が、東北、近畿地方、函館近郊などの高齢者の間では一般にジャガイモの別名
にもなっております。これは、生育期間が短く、温暖なところでは夏と秋の二
度収穫できることから来ております。 遠山地方では春作ジャガイモのみで、
その後作にはソバを植える農家が多い。品種はひとつではなく、いくつかの品
種を含みます。村内の料理店や民宿などでは8月以降に出され、蒸したり、皮
をむかずに煮たり、味噌だれで焼いて食べたりします。
一方、南信濃村の八重河内などで作られているジャガイモは特に「下り
芋」と呼ばれ、遠州からヒョウ越峠を越えてやってきたといわれていま
す。八重河内の民宿このたでは、下り芋の料理が味わえます。
平成14年3月14日、「遠山の二度芋の味噌田楽」が長野県の選
択無形民俗文化財に指定されました。標高の高い急斜地で作られる二度芋が、
山間部の畑作文化を現在に伝える貴重な財産であると認められもの。
この二度芋田楽は、皮をむかずに茹でたジャガイモを竹串に3,4個刺して、
味噌タレをつけて囲炉裏の炭火で炙ります。タレは在来種のクルミ、もしくは
縄文中期来6千年もの歴史をもつエゴマを炒ってから擂り鉢でよく擂り、味噌
と砂糖・みりん・酢など少々加えて練って作る。ねぎ味噌でも美味しい。
遠山郷では、囲炉裏の炭火が、飯を炊くにも、調理するにも使われ
生活の中にも位置づいていた。自家製炭をしている農家があるほど、炭火に対
するこだわりがあり、五平餅や蕎麦焼き餅をつくるにも、炭火が用いられてい
た。囲炉裏の存在が「二度芋の味噌田楽」というこの郷土食を生み出したとい
える。(「南信濃村の文化財」より)
質問・疑問・事例 か
ら検索へ行く
*エッセイ& Part Ⅱ *
へ戻る
*用語からの検索へ行く*
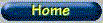 ホ
ームページ<スタート画面>へ戻る
ホ
ームページ<スタート画面>へ戻る

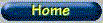 ホ
ームページ<スタート画面>へ戻る
ホ
ームページ<スタート画面>へ戻る